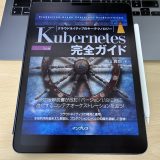ドメイン駆動設計(DDD)の”バイブル”として知られる、分厚く難解なこの一冊。
書店で手に取って「これは読めない」と諦めた方は少なくないのではないでしょうか?
自分も長らくその一人でした。
DDDに興味を持ったきっかけは、実務でコードの複雑さに直面し「値オブジェクト」という概念に出会ったことでした。
それから入門書を何冊か読み、実務で小さなプロジェクトにDDDの考え方を取り入れる中で、迷う機会が度々ありました。
そんなとき

提唱者であるエリック・エヴァンスはどう考えていたんだろう?
と疑問が必ず浮かぶように。
その答えを知るために、重い腰を上げてついに本書に挑戦しました。
この記事では、「エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計」を読み終えて得られた学びと、これから本書を読もうとしている方へのメッセージを、包み隠さずお伝えします。
結論から言ってしまうと、本書は、前提知識があれば挫折するほど難しくありませんでした。
もちろん、本書は決して簡単な本ではありません。
分厚い上に聞き慣れない概念や専門用語が次から次へと出てきます。
しかし、私が挫折しなかったのは、先に『ドメイン駆動設計入門』や『ドメイン駆動設計をはじめよう』といった入門書を読んでいたおかげです。
これらの入門書で断片的に学んだ「ユビキタス言語」「集約」「リポジトリ」といった概念が、本書では提唱者本人の言葉で体系的に整理されています。
まるでパズルのピースが次々と埋まっていくような感覚でした。
単なる技術書の読書というより、提唱者であるエリック・エヴァンス氏から授業を受けているような、不思議な没入感がありました。
本書は、小手先の実装テクニックを学ぶ本ではありません。
ソフトウェア設計の思想そのものを深く学び、自分の思考を根本からアップデートしてくれるような一冊です。
本書を読んで最も感動したのは、DDDが単なるコードの書き方ではなく、「ビジネスの成長を支えるための設計思想」であることを深く理解できたことです。
特に印象的だった2つの概念と、本書の普遍性をご紹介します。
1. 「蒸留」が示す、コアドメインを育てるという視点
入門書では実装パターンに焦点が当てられがちですが、本書ではコアドメインやシステム全体を育てるプロセスに多くのページが割かれています。
中でも「蒸留」という概念に今後役立ちそうな点を見出しました。
私は実務で「コアドメイン」の認識にズレがあったり、自分の頭の中が整理しきれていなかったりする経験がありました。
機能追加やリファクタリングをしようにも、何が本質で何がそうでないのかがわからず、途中で設計がブレてしまうことがよくあります。
しかし、本書で「ドメインビジョン声明文」や「蒸留ドキュメント」といったツールを知り、この悩みが解消されそうな期待を持ちました。
「蒸留」というプロセスを通じて、開発チームがビジネスの核となるドメインを整理し、共有していくことの価値を本書は明確に示してくれます。
コアドメインを継続的に「蒸留」していくことこそ、DDDが長期的なプロジェクトで真価を発揮する鍵のひとつなのだと学びました。
2. 「ポリシー」が解消してくれた、実装における小さな悩み
もう一つ、非常に印象的だったのが「ポリシー」という概念です。
実務でコードを書いていると、さまざまなビジネスルールや制約に直面します。
「この金額を超えたら送料が変わる」「この条件下では手数料が発生する」といったルールが、あちこちに散らばってしまうことがあります。
私はこれまで「これを分散させないためにはどうしたらよいのだろう?」と小さな悩みを抱いていました。
本書では、こうしたビジネスルールや制約を「ポリシー」という一つの概念として捉え、独立したオブジェクトとして表現できることを教えてくれました。
これにより、ビジネスルールが他のコードから切り離され、変更や管理が非常に楽になります。
この発見は、これからの設計に積極的に取り入れたいと感じています。
3. 今も通用する「DDDの神髄」は “対話・設計・実装のフィードバックループ” にある
「エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計」は2003年の出版ですが、その内容は現代のソフトウェア開発にも十分通用します。
それは、「ドメインエキスパートと認識を合わせながら、業務を設計・実装に落とし込み、修正サイクルを回す」というDDDの神髄が、サービスの開発スピードが上がった今だからこそ、より重要になっているからです。
開発者が業務からかけ離れた実装をすると、どこかで必ず歪みが生まれ、それが将来の速度低下につながります。
DDDは、この歪みを未然に防ぎ、サービスを長期的に成長させるための羅針盤のような役割を果たしてくれるでしょう。
もしあなたが本書を読もうか迷っているなら、やはり入門書を読んでからの挑戦をおすすめします。
特に、以下の2冊は本書を読む上で強力な助けとなります。
- 『ドメイン駆動設計入門』
- DDDの基本的な考え方と、それを支える実装パターンを分かりやすく解説しています
- 『ドメイン駆動設計をはじめよう』
- DDDの進め方やプロジェクトへの適用方法を実践的に学べます。
これらの本でDDDの基礎固めをしてから本書を手に取れば、きっと私のように挫折することなく、より深い学びを得られるはずです。
この記事では、「エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計」を読み終えて得られた学びと、これから本書を読もうとしている方へのメッセージを、お伝えしました。
「エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計」は、単なる技術書ではありません。
あなたのエンジニアとしての思考をアップデートしてくれるような、哲学的な一冊です。
分厚い本を読み切った達成感は、エンジニアとしての自信にもつながります。
もしあなたが『ドメイン駆動設計入門』などの本を読み終え、次のステップに進みたいと考えているなら、ぜひこの「起源」となる本を手に取ってみてください。
きっと、あなたのソフトウェア開発に対する視座を一段高いところに持ち上げてくれるはずです。